看護部教育研修「人生の最終段階のケア」を行いました
緩和ケア認定看護師 長田 恵美
先日、院内研修をおこないました。お題はズバリ!「人生最終段階のケア」です。日本は、高齢者が最期を迎える場所として病院が8割を占めている現状があります。当院は緩和ケアだけではなく慢性期の機能もあり、院内どの場所でも患者さんの人生の最期の時間を共に過ごすことは少なくありません。最期をどのように迎えたら良いか、その過程で医療従事者として自分たちに何ができるのか、学ぶ場として企画されました。
本人の思いを共有することは勿論、医療関係者間でも様々な話し合いを行い、本人の思いを尊重したケアを目指せるようにと願いを込めて講義をおこないました。
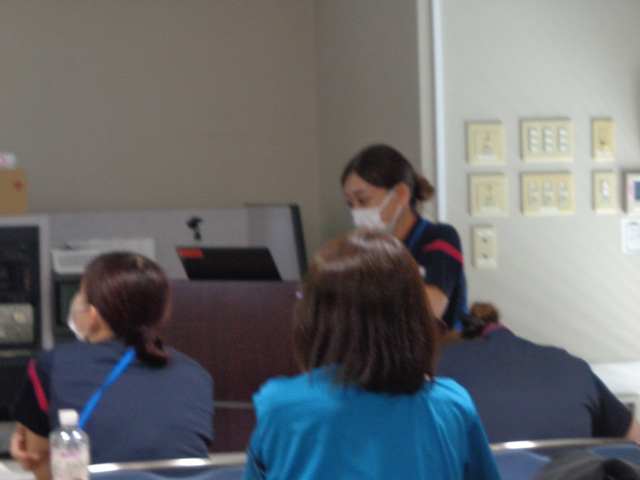
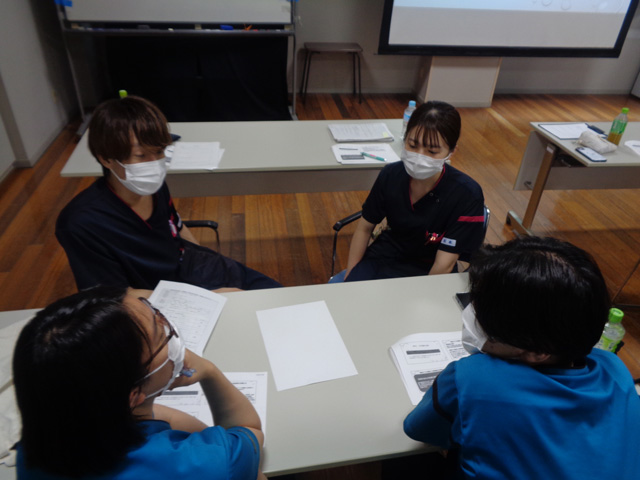
私は言葉の定義的な所を頭に入れておくことも大事だと考えているので、「終末期ケア」「ターミナルケア」など言葉の整理を行い、厚生労働省が提唱している「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」や当院でも使われている「事前指示書」について、理解を深めてもらいました。
最後に、グループワークで看取り期における悩みなどを共有しました。誤嚥リスクがある中で「食べたい」という患者の思いをどのようにとらえ、介入したら良いか、検査や点滴などの医療行為の必要性の判断など、様々な悩みが表出されました。
どの様に過ごしたいか、思いや考えはひとそれぞれです。答えは一つではないので、患者さんの思いをしっかりと汲み取る姿勢を忘れず、これからも頑張っていきましょう!
摂食・嚥下障害看護認定看護師 加藤 久美子
2014年、3名からスタートした「専門・認定看護師委員会」は、今年で10年目。
そこで節目となる今年、専門・認定看護師を院内に浸透させたい思いとメンバーの結束力を高めるためにキーホルダーを作成しました。キーホルダーは「専門・認定看護師委員会」の発足者である看護部長が作成した下記のモチーフを使用しました。このモチーフは四葉のクローバーに専門・認定看護師の役割を表記しています。四葉のクローバー1枚1枚には「誠実」「希望」「愛」「幸運」の意味があり、4枚揃うと「真実・本物の力」を表します。果たすべき役割と四葉にあやかりたいとの願いをこめて作成しています。
キーホルダーは専門・認定看護師の胸元の名札につけていますので、探してみてください。

鶴巻温泉病院の専門・認定看護師のモチーフ

キーホルダー(表面) キーホルダー(裏面)

キーホルダーは胸元につけています
感染管理認定看護師 前田奈美江
5月31日、6月1日につくば国際会議場で開催された第12回日本感染管理ネットワーク学会学術集会に参加してきました。今年度も様々なシンポジウムや教育講演等がありました。
学会に参加して困る点として聴講したい内容が重なることが多々あります。コロナ前はどれか1つに絞って聴講するか、参加した仲間同士で情報共有することが精一杯でした。しかし、現在は主要な講演や発表、シンポジウム等がオンデマンド配信されるようになり、聴講できなかったものも後から聴講できる機会があります。コロナ禍で大変なことも多いですが、学会参加後も学べるシステムが整備されたことは唯一の救いと思います。
学会に参加する際の楽しみとして、ランチョンセミナーのお弁当があります。大人気で事前申し込みが早期に締め切られてしまうことが多いのですが、稀に当日朝にチケットが入手できる場合があります。今回は運よくチケットが入手できましたのでお弁当を美味しくいただきながら学んできました。

学会・ランチョンセミナーのお弁当