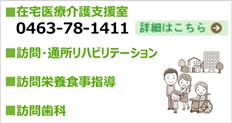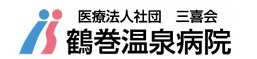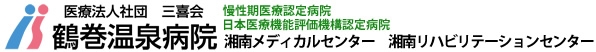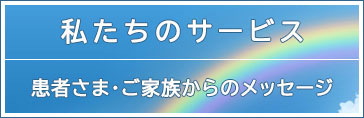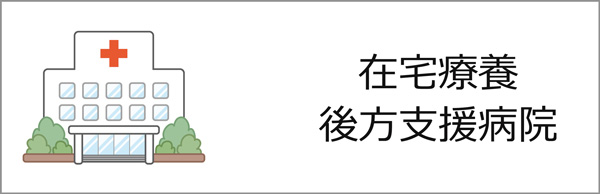障がい者・難病リハビリ病棟の取り組みをお伝えします
障がい者・難病リハビリ病棟では、重度の障がい者や、進行期の難病、特に神経難病の患者さまに、医療・看護・介護・リハビリテーションを通して、多職種で、その人らしく生きるためのお手伝いをしています。在宅療養中の方には在宅サポート入院(レスパイト入院)をご利用いただいております。
ジュウマンブンノイチ ダメ親父のALS闘病記 2015
2015年 1月 筋萎縮性側索硬化症
入院での検査も終わり結果を聞くため個室に呼ばれた。血液、髄液、二酸化炭素量など問題ないらしい。ホッとするどころか嫌な予感しかしなかった。
運動ニューロンの病気ですねと言われた。病名はと尋ねると、病名を付けるとするならば筋萎縮性側索硬化症でいいでしょうと言われた。すなわちALSだ。あきれて涙も出なかった。宝くじも当たったこともないのに十万人に一人の難病、こんなものばっか当たらないでよと思った。
仕事はどうするの、住宅ローンだってやっとあと二年まで来たのにとDrに食って掛かってみたもののどうにかなるものでもなかった。これからの過ごし方などを説明していたと思うが、頭の中が真っ白になりよく覚えていない。確かとろみがついたものを食べるようになるとか、今すぐどうこうなる病気ではないので人生の終い支度をしなさいとか言われたようだ。この言葉の意味は一年後、思い知らされることとなる。
ジュウマンブンノイチ ダメ親父のALS闘病記 2016(1)
2016年 1月 大盛りのご飯
家の中では歩行器で歩いているが、歩行器ごと倒れてしまうことが多くなった。一度転んでしまうと一人では立ち上がることが出来なくなってしまいました。一人で家にいるときもし転んでしまって誰かに発見されるまで倒れたままでいると思うと恐怖を感じ、トイレに行くのも怖くなってしまいました。
自分で風呂に入ることが出来なくなってしまった今、風呂に入れてもらうためディに通っていると思えば少しは気が楽になった。家では経管栄養がメインでディでの昼食が楽しみだと知った所長が、毎日大盛りのご飯を腹いっぱい食べさせてくれた。
ジュウマンブンノイチ ダメ親父のALS闘病記 2016(2)
2016年 7月 すべてのことがリハビリ
おそらく発病から2年が経過したとみられる。2年前はバリバリと仕事をしていた人間の今現在はというと、見る、聞く、考えるといったことに変化はないが運動能力に関しては止まることなく進行し続けて自分で呼吸すること以外、人様の力をお借りしないと何一つまともなことが出来なくなってしまった。この辺で進行が止まってくれないと後は呼吸障害が始まってしまうのか。本当に厄介な病気だ。

ナースコール・ベッドリモコン・テレビリモコンの工夫
ジュウマンブンノイチ ダメ親父のALS闘病記 2017
2017年 1月 初めての正月
入院して初めての正月を迎えることとなった。この病気を告知されてから丸二年が経過したことになる。その時二年後の生活がこんなことになっているとは想像もできなかった。ここに入院する前だが、D病院のDrに私の病気の進行具合はどんなものなのか聞いたことがある。超特急でもなければゆっくりでもないらしい。一般的に呼吸器を付けなかった場合の与えられた時間が数年とするならば、残された時間はあと二年ほどになるのであろうか。
もうおせち料理など食べることはないだろうと思っていたが、病院食で大好きな伊達巻や栗きんとんが出てきたので少しではあるが正月気分を味わうことが出来た。
ジュウマンブンノイチ ダメ親父のALS闘病記 「妻からのメッセージ」
ALS闘病記「妻からのメッセージ」
彼が入院してからも私の耳には時々彼の絶叫が聞こえて来た。その時彼が私を強く要していたのか、フラッシュバックだったのか。
彼が肺炎になってから 私も時々胸が痛く苦しくなった。彼の苦しみが頂点に達した時だったのだろうか。
7月22日 早朝 彼は旅立った。51歳の誕生日を迎えて10日目だった。自覚から3年、確定から2年3ヶ月、仕事を辞め2年、入院から1年2ヶ月だった。
入院生活について ~療養型の病院とは?~
療養型の病院とはどんなところでしょうか?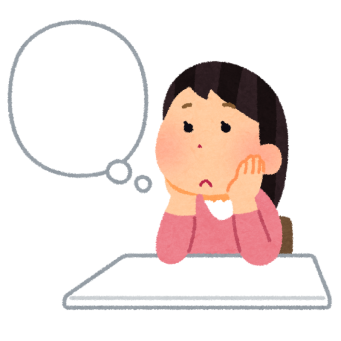
入院相談でお問い合わせいただくことも多く、病院での生活や療養環境について、イメージが沸かない方もいらっしゃるのではないか...?と感じています。
そこで、少しでも当院の療養環境を知っていただく機会になればと思い、今回は当院の障がい者・難病リハビリ病棟における入院生活の一場面をご紹介いたします。
正面玄関
病院の入り口です。入院退院専用の駐車場があり、自家用車や介護タクシーを駐車して乗り降りができるスペースがあります。入院当日は入り口で担当者がお待ちしていますので、安心してご来院ください。