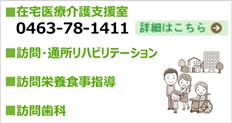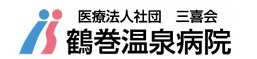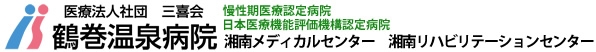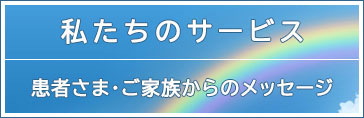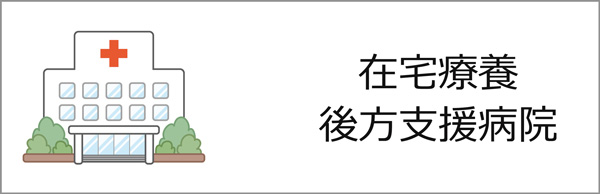- HOME
- 障がい者・難病リハビリ病棟スタッフコラム
- チーム紹介
嚥下内視鏡検査(videoendoscopic evaluation of swallowing : VE)について
神経難病では病状の進行とともに高率に嚥下障害を合併し、食事中のむせ込みが目立つようになり時には肺炎発症に至ります。肺炎を始めとした重篤な病状において経口摂取ができない期間が続くと、さらに嚥下機能障害が進行します。患者さんの生活の質(QOL)向上のため嚥下機能の維持は重要な要素です。嚥下リハビリテーションの可否・必要性や適切な食形態を決定するためには嚥下機能評価が必須です。
嚥下機能評価検査には嚥下内視鏡検査(VE)と嚥下造影検査(VF)がありますが、VEは検査室に移動せずベッドサイドで容易に施行可能で、放射線被ばくがないことがメリットです。
VE検査では喉頭内視鏡(カメラ)を鼻から挿入し、カメラの先端が咽頭(のど)に達すると喉頭蓋(気管の蓋)、声帯、食道入口部が観察できます。まずは咽頭内の唾液の溜まり具合や咳の反射の起こりやすさを判定します。

嚥下内視鏡検査(VE)
その後、少量の着色トロミ水やゼリーを飲み込んでもらいます。飲み込むタイミングではカメラには何も映らなくなり(ホワイトアウト)、飲み込む様子そのものは観察できませんが、飲み込みが起こるタイミングや飲み込んだ後の咽頭内の残留物の程度を観察することにより、嚥下状態を類推することができます。
上記の観察結果をスコア化(一般的には兵頭スコアが用いられます)し、スコアにより嚥下訓練の可否や訓練の程度を判定します。
【閲覧注意】嚥下内視鏡検査(VE)動画です。喉頭内視鏡(カメラ)を鼻から挿入し、咽頭部の動きの状態を観察します。

【閲覧注意】クリックでVEの動画(YouTube)が表示されます。字幕ONで簡単な説明が表示されます。
鶴巻温泉病院 障がい者・難病リハビリ病棟 医師 清水 学
食べる楽しみの支援 ~おいしい・また食べたい~
障がい者・難病病棟には病気の進行により、お口から食べることが難しくなる患者様がいます。そのため言語聴覚士は少しでも長く食べる楽しみを感じて頂けるよう支援しています。
言語聴覚士が行う支援の一つとして、誕生日などの特別な日に主治医の許可の下、やわらかく調理された介護食品や飲み込みやすく加工した嗜好品を、誤嚥・窒息に配慮した設定で味わって頂くことがあります。
下の写真は飲み込むことが難しい患者様でも食べられるように加工した年越しそば(とろろそば)です。リハビリの時間に作業療法士と管理栄養士が協力して、麺から作りました(うどんに見えるかもしれませんが・・・)。
今後も患者様が食べる楽しみを感じてもらえるよう支援していきたいと思います。
年越しそば (とろろそば)
【貼り薬について】薬剤科
貼り薬は皮膚に貼付して薬の効果を発揮させる製剤です。
貼付部位で局所的に効果を発揮する薬剤が一般的に馴染み深いと思いますが、最近は皮膚から吸収され血中に入った薬剤が全身に作用する「経皮吸収型製剤」も増えています。

局所で作用するものには
- 消炎鎮痛効果のある湿布薬
- 表面麻酔作用のあるテープ剤
などがあります。
湿布薬には熱をもった患部に使用するメントール(ハッカ油)等が配合された冷湿布、血行不良による痛みをもった患部に使用するトウガラシエキスが配合された温湿布があります。
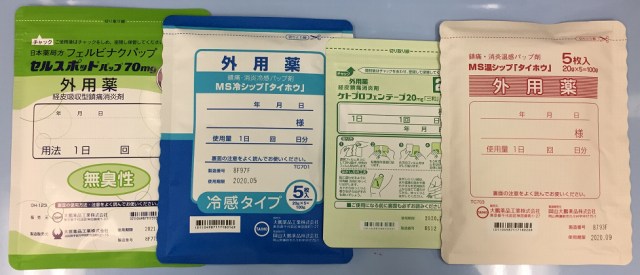
病院から地域へ 医療ソーシャルワーカー
障がい者・難病リハビリ病棟では、リハビリ目的、在宅サポート入院(レスパイト入院)、長期療養目的で入院をされている方がいます。リハビリ、在宅サポート入院(レスパイト入院)目的で入院をされている方は一時的な入院であり、入院生活が終わると、住み慣れた地域での生活を再スタートされます。
地域での生活を開始する前に必要なことが、地域との連携です。在宅生活をする中で介護保険や障害福祉サービス等の社会資源サービスを利用する場合には、在宅関連機関(かかりつけ医師・ケアマネジャー・訪問看護・ホームヘルパー・福祉用具等)との連携がかかせません。

重度訪問介護を利用した入院中の外出
2018年の4月より国の制度として、重度訪問介護を利用した入院中の外出が可能となりました。
当病棟でも、重度訪問介護を利用し、週に1度、近隣散策や公共交通機関を利用した外出、買い物などを楽しまれている方がいます。
今では「今度はみんなに会いに行きたい」「海を見に行きたい」など、少しずつ外出範囲が広がってきています。そのため、今後も患者様の社会参加が促せるよう支援していきたいと思います。


重度訪問介護を利用し外出(買物)
※患者様の同意を得て写真を掲載しています。
リハビリテーションの紹介(2)
当病棟ではチームで患者様の目標を共有し、その人に合わせたリハビリテーションを提供することを心掛けています。今回は、その一部を紹介します。
作業療法
患者様一人ひとりの希望を聴取し、日常生活を送るための練習や環境の調整、患者様・ご家族が大切にされている活動(外出・外泊・調理・手芸など)を継続するための支援を行います。
↑自助具箸を作成
「介助ではなく、自力でそばを食べたい」「もともと、箸を使って食事をするのが好きだったんだよね」と話される患者様と一緒に、試行錯誤しながら自助具箸を作成しました。その結果、お蕎麦をお一人で食べることができるようになりました。あきらめていた活動を支援することで、患者様の主体性を引き出すことができ、今後の生活を前向きに捉えることが可能となりました。
現在、この患者様は「自分で車いすを漕いでコーヒーを飲みに行きたいな」と話しており、次の目標に向かい練習中です。