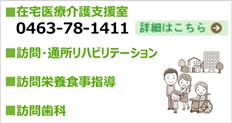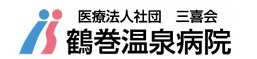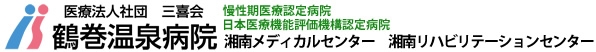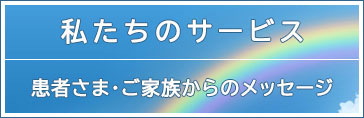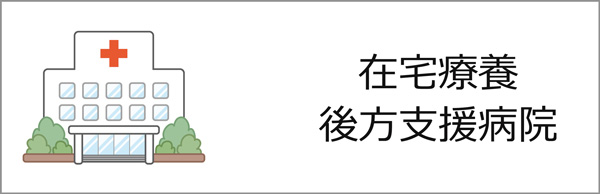- HOME
- 障がい者・難病リハビリ病棟スタッフコラム
- 病棟紹介
神経難病の治療と病棟の役割|第3診療部 中島 雅士
2017.08.06
今回のスタッフ・コラムでは、神経難病の治療と、その治療におけるわれわれの障害者・難病リハビリ病棟の役割について説明します。神経難病にはいくつかの種類がありますが、その多くは成人してから発症し、しゃべる、食べる、歩く、排泄する、などの日常生活に必須の機能が徐々に害(そこな)われていきます。
病気の始まる年齢も疾患によって異なりますが、早くは30歳代から、遅い場合でも60歳代に始まることが多く、日常生活だけではなく、仕事や今後の人生設計についての見直しを迫られます。
初期神経難病の診断と治療

神経難病の診断は難しいものではありません。経験を積んだ神経内科医であれば、病気の経過を尋ねること(病歴聴取・問診)と身体所見の診察(神経学的診察)で、たとえ疾患の初期であっても80%以上の確率で診断できます。補助診断として核磁気共鳴画像検査(MRI)、脳代謝・血流検査(PETまたはSPECT)、筋電図、各種自律神経機能検査などがあり、これらの結果を総合して薬物をはじめとする治療方法を選択します。
しかし、神経難病を患う方々が求めることは、その診断名と治療だけではなく、自分の病気がどのような経過をたどり、その過程で現われてくる障害にどのように対処し、あるいは障害を受け入れてよりよい人生を送っていくことにあると思います。